「子どもはほめて育てろ」「やる気が大事」――よく聞く教育論やけど、ほんまに効果あるんか?
今回紹介する『「学力」の経済学』は、教育を”感覚”ではなく”データ”で考える本やで。
子育てや教育に関わる人にとって、目からウロコの話がぎっしり詰まっとる。
本の基本情報
- タイトル:「学力」の経済学
- 著者:中室牧子
- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 発売日:2015年6月
- ISBN:978-4-7993-1737-9
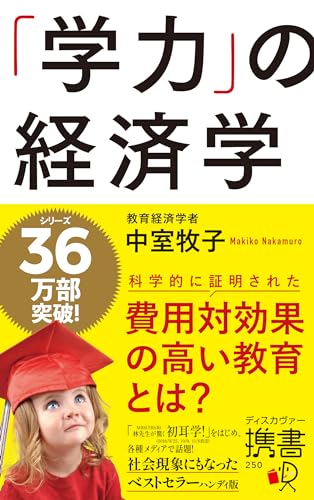
「学力」の経済学 (ディスカヴァー携書)
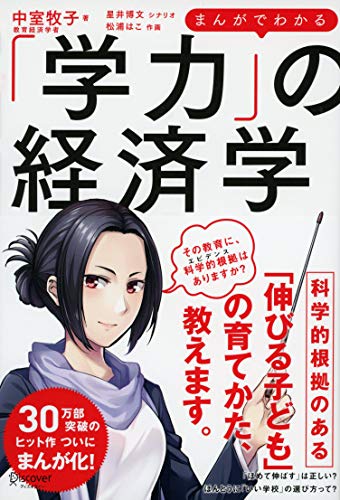
まんがでわかる「学力」の経済学
どんな人におすすめか?
- 子育てに悩んでる親御さん
- 教育現場で働く先生や指導者
- 「ほめ方」や「ご褒美」の使い方を科学的に知りたい人
印象に残ったポイント
「子どもは勉強したらご褒美をあげるべきか?」って議論、よくあるやろ?
でもこの本では、インプット(読書や宿題)にご褒美を与えると学力が上がるって、データで示されとるねん。
「テストでいい点とったらご褒美」よりも、「宿題したらご褒美」の方が効果あるんやって。
成績ってアウトプットやけど、それだけ褒めても何すればええか分からんから効果が薄い。これ、納得したわ。
それと、「少人数学級」や「子ども手当」みたいな政策も、
海外のデータでは「あんまり効果出てへんで」って結果が出とるらしい。
ずっと「少人数のほうが先生の目も届くし、ええに決まってるやん」って思ってたけど、
「ほんまにそのお金の使い方が一番効果あるんか?」っていう見方も大事なんやなって気づかされたで。
感想・気づき
「ほめ方」とか「ご褒美の使い方」とか、なんとなく感覚でやってたことに、
ちゃんとデータで裏付けがあるってのが、おもろかったし勉強になったわ。
あと、自分も「少人数学級=学習効果が高い」って思い込んどったけど、
国レベルの教育政策では「費用対効果」って視点もめっちゃ大事なんやって初めて考えた。
「ええことっぽい」だけで動くんやなくて、
「それって本当に結果に繋がってるん?」って立ち止まるクセ、持っときたいなって思ったわ。
読んで変えた(変えようと思った)行動
ある日、会社の先輩から突然言われてん。
「うちの子、アホすぎるねんけど、どうしたらええんやろ…?」って。
詳しい相談内容は書かんけど、正直、先輩もけっこう悩んでてな。
そこで、ちょうど読んでたこの本の話を思い出して、アドバイスしてみたんよ。
「点数で怒るより、宿題やったとか、本読んだとか、
“やった行動”に対してちゃんと褒めてあげたらええみたいやで」って。
先輩がそれを実践してくれてるかはわからんけど、
自分自身に将来子どもができたら、
結果ばっか見んと、毎日の頑張りに目を向けて声かけしたいなって思った。
まとめ・おすすめポイント
教育や子育てって、どうしても「感覚」や「経験」で語られがちやけど、
『「学力」の経済学』はそれを数字とデータで整理してくれる貴重な本や。
ちょっとでも興味あったら、ぜひ一度読んでみてや。
子どもと接するすべての人におすすめできる一冊やで。
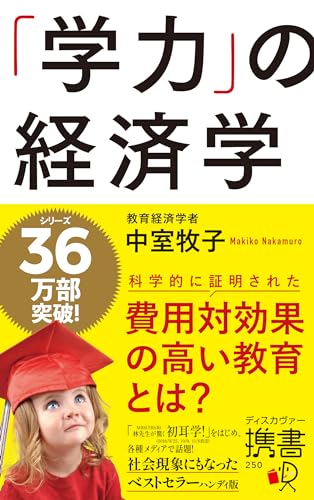
「学力」の経済学 (ディスカヴァー携書)
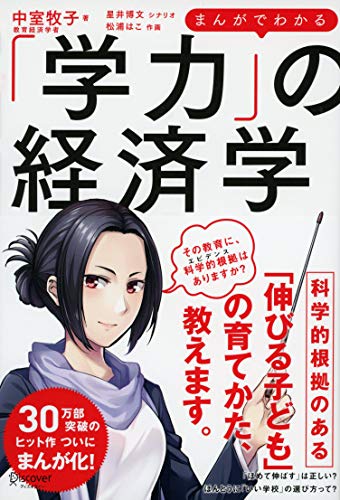
まんがでわかる「学力」の経済学
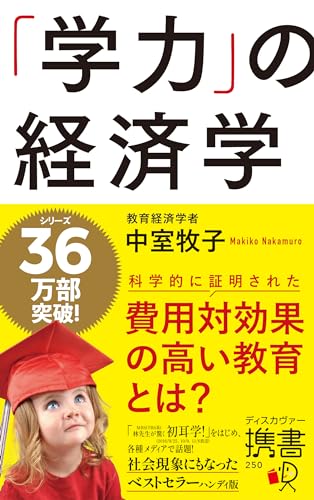


コメント